【光る君へ】なぜ、為時は10年も無官だったのに「越前守」に抜擢されたのか? 漢詩が「宋人との交渉」に役立った!?
日本史あやしい話54
■宋人との交渉で大活躍
事の発端は、朱仁聡なる宋人らが、70余名もの同国人を引き連れて、若狭国に来航してきたことに発している。若狭や越前周辺には、大陸から交易を求めて来航するものがあとを絶たず、当時の朝廷にとって、どう対処すべきか頭を悩ませていたという経緯があった。
交易を巡って、金銭面のトラブルだけでなく、暴行にまで及ぶようなこともあり、対応を迫られていたのだ。朝廷としては、できれば体良くお帰りいただいた方が有難いというのが正直な心持ちだったのかもしれない。
時は995年、対応に苦慮した道長が、「唐人来航の文」を一条天皇に奏上。結果、彼らを越前国に移した上で、受け取っていた羊などの献上品をも返却したというから、この時は体良く追い払うことができたのだろう。
この唐人来航の騒動を契機として、一条天皇自身も、日本海沿岸への人材派遣の重要性には気が付いていたはずである。ただ、問題は適任者がいないことであった。そこに奏上されてきたのが、漢詩文に長けたことで知られていた為時の一文である。天皇はもとより道長にとっても渡りに船。実に好都合な人物が現れたとでも思ったのだろうか。
これ幸いとばかりに飛びついたという訳である。為時なら、漢詩を通じて宋人とコミュニケーションをとることも可能。その才を交渉に生かしてもらいたいとの思いで、慌ただしく除目の変更と相成った次第であった。
それが功を奏したかどうか定かではないが、詩文の贈答を繰り返すことで、それなりに交流を深めることはできたようだ。
「国を去ること三年、孤館の月、帰程の万里、片帆の風」(国を去って三年、あなたは一人で鴻臚館において寂しく月を眺めておられるのですね。帰路は万里の道のりではありますが、片寄せた帆でも順風が吹けば帰国することもできましょう)と、為時が唐人(宋人の羌世昌とも)に送った文面が、それを物語っているかのようである。
ちなみに、任地へは娘の紫式部も同行しているが、漢文にも長けた自慢の娘だっただけに、宋人との交渉に一役買ってもらおうとの腹積もりがあったのかもしれない。
- 1
- 2

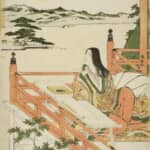


-e1704957789649-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
